| 母子健康協会 > ふたば > No.69/2005 > 保育と食育 > 2.子どもの健康と甘味 〜適切な砂糖の使用〜 > 小児肥満の現状 | ||||||||||||||
前川 では、引き続きまして、大和田先生に、「子どもの健康と甘み(砂糖)」について、お話をいただきます。大和田先生は、女子栄養大学小児栄養学の教授でいらっしゃいます。本来は、先天性代謝異常、フェニールケトン尿症の専門の方で、栄養に非常に造詣の深い先生です。先生、よろしくお願いいたします。 大和田 はじめまして。本年度から女子栄養大学に移り、小児栄養学を担当しております大和田です。どうぞよろしくお願いいたします。 講演要旨に「甘み」と記載いたしましたが、この語句は蔗糖(一般名「砂糖」)の意味で使用いたしました。近年、砂糖は「悪者」と言われることが多いように思います。確かにむし歯の発生に砂糖は大きく関わっております。しかし、「むし歯になるから砂糖を与えない」と言う考え方は誤りです。砂糖を含めた“糖質”は、三大栄養素の1つで、ヒトにとって大切な栄養素であります。幼児期以降、ヒトが摂取する糖質の大部分は多糖類である「でんぷん」ですが、分子が小さく「甘い」糖質、例えば二糖類である蔗糖、単糖類である果糖などの摂取が子どもの発育に果たす役割について、小児科医として研究して参りました。そこで、本日は小児の肥満並びに2型糖尿病を取り上げ、それらの発症と砂糖との関わりについての私どもの仕事をお話したいと思います。
日本では、小児の肥満が増加していることが統計学的にも明らかにされていますが、これは主に学童(小・中学生)での調査成績で、毎年、新学期に文部科学省が学童に義務付けている身体計測に基づいております。最近の成績では、小中学生の約10%に肥満傾向を認めると報告されています。これに対し、幼児期は学童に比べると肥満傾向児の頻度は高くはありませんが、学童肥満の増加の基礎には幼児期の食生活、食習慣が関与していることは明らかです。 そして、幼児期の集団保育にかかわっておいでの皆様が「小児肥満」についての理解を深め、園児および保護者の方々に適切に接して下さることが、その後の学童肥満を予防するための良い手段になります。 1 肥満の分類、成因と評価方法 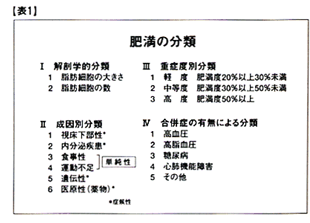 表1に示すように、“肥満”は様々な角度から分類されていますが、臨床の場では何故肥満になるのか、即ち、病因による分類が先ず行われます。その中で、脳腫瘍や頭部外傷など種々の原因で生じる視床下部性の肥満、クッシング症候群や甲状腺機能低下症など内分泌疾患に伴う肥満、染色体異常症やその他の遺伝性疾患に伴う肥満および副腎皮質ステロイド等の薬剤使用による医原性肥満などを症候性肥満と呼びますが、これらは子どもの肥満の数パーセントを占めるに過ぎません。小児肥満の大部分、約95%は“単純性”肥満で、食事摂取量過多と運動量低下のために生じるものと考えられます。 表1に示すように、“肥満”は様々な角度から分類されていますが、臨床の場では何故肥満になるのか、即ち、病因による分類が先ず行われます。その中で、脳腫瘍や頭部外傷など種々の原因で生じる視床下部性の肥満、クッシング症候群や甲状腺機能低下症など内分泌疾患に伴う肥満、染色体異常症やその他の遺伝性疾患に伴う肥満および副腎皮質ステロイド等の薬剤使用による医原性肥満などを症候性肥満と呼びますが、これらは子どもの肥満の数パーセントを占めるに過ぎません。小児肥満の大部分、約95%は“単純性”肥満で、食事摂取量過多と運動量低下のために生じるものと考えられます。肥満の判定には表2の方法が一般的に使用されます。即ち、乳児期〜幼児期前半には、旧くからカウプ指数と言う数値が用いられています。カウプ指数はグラムで表した体重をセンチメートルで表現した身長の2乗で割り10を掛けた数値です。この指数が20以上だと肥満傾向、22以上では肥満と評価されます。 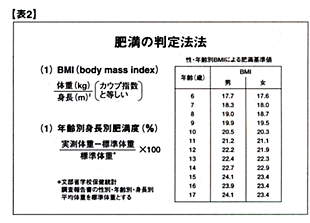 カウプ指数は、成人に広く使用されているBMI(body mass index)と等しい指数で、体重(Kg)を身長(m)の2乗で除した値です。成人ではBMIが25以上の場合に肥満と判定します。一方、わが国では学童期の肥満判定に“年齢別身長別肥満度”(以下肥満度)と言う指標が広く使用されています。肥満度算出の基本となる年齢別身長別の平均体重(標準体重と称します)は、上述の文部科学省の行っている身体計測結果から得られています。この肥満度という指標は国際的な指標ではないのですが、学童期の身体発育には性差がみられるため、身長と体重から単純に決定されるBMIよりも、男女差を考慮している点で適切な指標であろうとの考えから、わが国の多くの小児内分泌専門医がこの指標を用いております。また、性・年齢別BMIという指標も一部で使用されております(表2参照)。 カウプ指数は、成人に広く使用されているBMI(body mass index)と等しい指数で、体重(Kg)を身長(m)の2乗で除した値です。成人ではBMIが25以上の場合に肥満と判定します。一方、わが国では学童期の肥満判定に“年齢別身長別肥満度”(以下肥満度)と言う指標が広く使用されています。肥満度算出の基本となる年齢別身長別の平均体重(標準体重と称します)は、上述の文部科学省の行っている身体計測結果から得られています。この肥満度という指標は国際的な指標ではないのですが、学童期の身体発育には性差がみられるため、身長と体重から単純に決定されるBMIよりも、男女差を考慮している点で適切な指標であろうとの考えから、わが国の多くの小児内分泌専門医がこの指標を用いております。また、性・年齢別BMIという指標も一部で使用されております(表2参照)。2 肥満の発症時期と成人肥満への移行 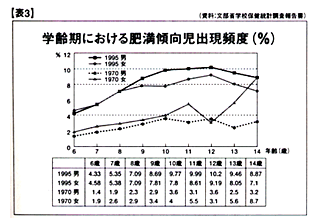 1995年に厚生省(現厚生労働省)が示した離乳食の改定基準において、離乳期には肥満傾向を認めてもそれほど心配しなくて良いとのコメントが付記されています。欧米からも、「良性肥満、悪性肥満」の考えが1980年代に提唱され、2歳未満の肥満を良性に位置づけています。また、日本からも、生後3〜4か月時のカウプ指数は近年減少傾向にあるとの報告が見られます。ところが、3歳以後は漸次カウプ指数の増加が各所で見られるようになり、学童期になると肥満度20%以上を示す児の比率が近年、有意に増加しています。例えば、6歳〜14歳の学童における肥満傾向児の比率を1970年と1995年で比較すると表3のように25年の間に2倍以上に増加し、2001年の調査では、9〜14歳の男子では平均10・7%、女子では平均9・1%が肥満度20%を超えておりました。そして、学童期の肥満は成人肥満に繋がることが多いことが小児科からも、内科領域から指摘されておりますが、疫学的成績は明らかではありません。 1995年に厚生省(現厚生労働省)が示した離乳食の改定基準において、離乳期には肥満傾向を認めてもそれほど心配しなくて良いとのコメントが付記されています。欧米からも、「良性肥満、悪性肥満」の考えが1980年代に提唱され、2歳未満の肥満を良性に位置づけています。また、日本からも、生後3〜4か月時のカウプ指数は近年減少傾向にあるとの報告が見られます。ところが、3歳以後は漸次カウプ指数の増加が各所で見られるようになり、学童期になると肥満度20%以上を示す児の比率が近年、有意に増加しています。例えば、6歳〜14歳の学童における肥満傾向児の比率を1970年と1995年で比較すると表3のように25年の間に2倍以上に増加し、2001年の調査では、9〜14歳の男子では平均10・7%、女子では平均9・1%が肥満度20%を超えておりました。そして、学童期の肥満は成人肥満に繋がることが多いことが小児科からも、内科領域から指摘されておりますが、疫学的成績は明らかではありません。3 肥満傾向児増加の背景 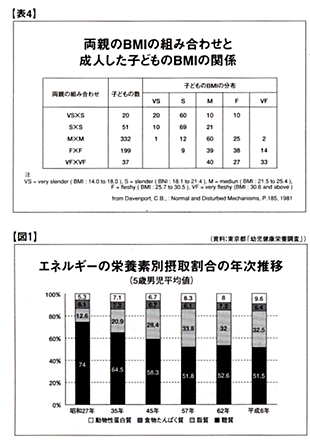 摂取エネルギーが消費エネルギーを上回る状態が、ある程度以上の期間持続した場合に「肥満」を生じると考えて良いと思いますが、肥満が成立するためには環境因子とともに、遺伝因子が関与するようです。1980年代には、すでに肥満の遺伝に関する様々な研究結果が欧米から報告されています。例えば、1981年には、高度肥満の両親の子どもには肥満児の頻度が高く、著しく痩せている両親には高度肥満の子どもはいないと言う成績が639人の子どもとその両親を調査して報告されています(表4)。このような傾向はわが国でも同様で、小児肥満の日常診療の場でよく遭遇すると思います。 摂取エネルギーが消費エネルギーを上回る状態が、ある程度以上の期間持続した場合に「肥満」を生じると考えて良いと思いますが、肥満が成立するためには環境因子とともに、遺伝因子が関与するようです。1980年代には、すでに肥満の遺伝に関する様々な研究結果が欧米から報告されています。例えば、1981年には、高度肥満の両親の子どもには肥満児の頻度が高く、著しく痩せている両親には高度肥満の子どもはいないと言う成績が639人の子どもとその両親を調査して報告されています(表4)。このような傾向はわが国でも同様で、小児肥満の日常診療の場でよく遭遇すると思います。一方、環境因子としては、食習慣の変化が肥満の発症に大きく関わっていると思います。図1に東京都が行った幼児の栄養調査の中から5歳男児の結果を示します。即ち、昭和27年(1952年)から平成6年(1994年)における三大栄養素の摂取比率の推移を追跡しますと、1980年代から糖質摂取の減少と脂肪摂取の増加が進行しています。また、たんぱく質特に動物性たんぱく質摂取の増加も顕著です。同様の傾向が、日本人全体の三大栄養素平均摂取比率にも認められております。脂肪および動物性たんぱく質摂取増加と糖質の減少と言う日本人の食習慣の変化が、小児肥満増加に影響を与えていることは明らかだと思われます。これらの結果を見ますと、小児肥満の増加の原因を「甘み」のみに帰することはできません。
|
||||||||||||||
| 母子健康協会 > ふたば > No.69/2005 > 保育と食育 > 2.子どもの健康と甘味 〜適切な砂糖の使用〜 > 小児肥満の現状 |
|