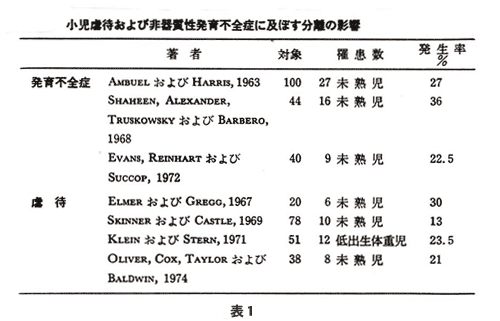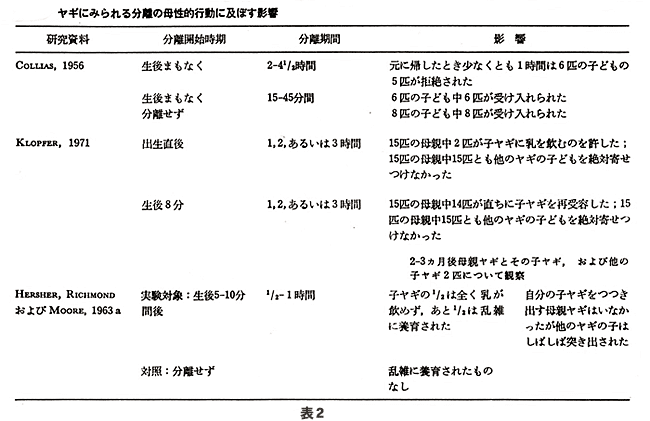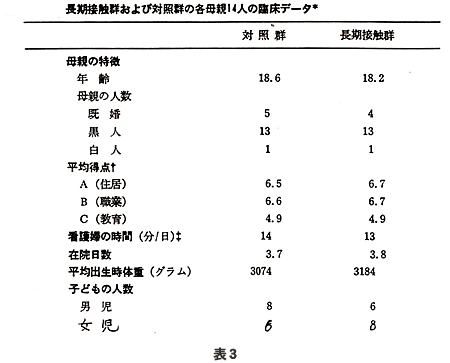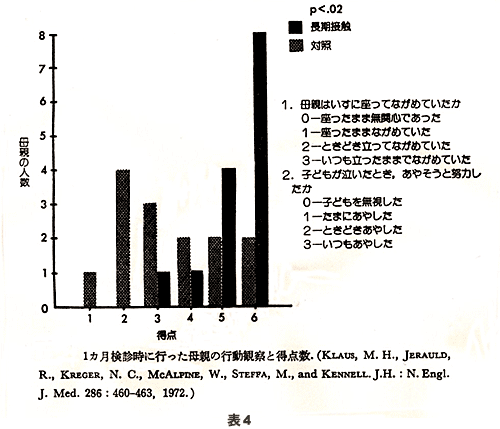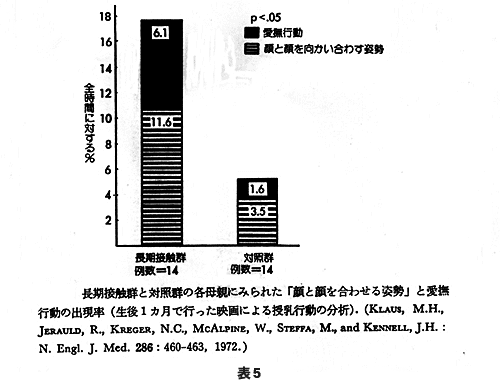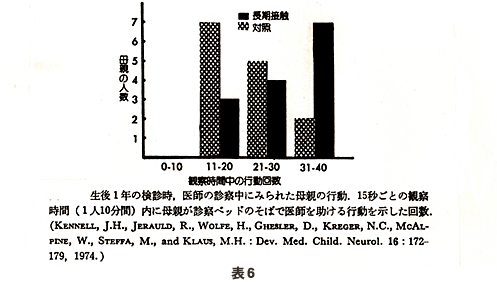| 母子健康協会 > ふたば > No.71/2007 > 子どもが育つ保育 > 1.ふれあいの意味 > 新生児期における「ふれあい」の重要性 | ||||||||||||||||||
「ふれあいがどうして重要かということを理解するためには、新生児期におけるふれあいの重要性を理解していただくのが一番の早道です。妊娠中のお母さんたちには、子どもを育てるエネルギーが遺伝的に組み込まれておりますし、お腹の中の赤ちゃんにも育つ力が遺伝的に組み込まれていますが、両方のエネルギー共に、お産しただけでは出てこないのです。引き出されないと出てこないというところが大切なことです。それは、お産をした後のお母さんと赤ちゃんの自然に行われるスキンシップ、ふれあいによってスイッチが入ることになっています。このための一つの能力として、新生児が持っている不思議な能力があります。生まれたばかりの赤ちゃんはいろいろなものをすべて見ますが、人間の顔を一番よく見て、最も見える距離が母乳をやっているときのお母さんの目と赤ちゃんの目です。その距離で抱いてお母さんが語りかけると、赤ちゃんはそれに応えるように、体を揺すったり、口を動かしたりします。生後5日以上たつとお母さんのにおい、呼び声で、そっちを振り向くなどのことが、わかっているわけです。 普通の望まれた妊娠で周囲に支援がありますと、胎動が始まる頃から、どんな赤ちゃんが生まれるのだろうかとの期待と不安があります。生まれた後はどんな人種のお母さんたちも、必ず抱いたり、さすったり、母乳を与えたり、自然のスキンシップを行います。それに対して赤ちゃんが持っている能力で応えますと、それで初めて、組み込まれていた子どもを育てるエネルギーと、子どもの育つ力にスイッチが入るわけです。 新生児の早期接触がどうして重要かということに関しましては、表1を見てください。
これは、第二次世界大戦の後、アメリカで、何だかわからないけれども、大きくならない、発達が遅れている発育不全の子どもと虐待が問題になったわけです。発育不全症の子どもでは100人いたうちの27%が、生まれた後、お母さんと分離されていたとか、虐待の子どもでも、虐待されたうちの13〜30%が周産期にお母さんと一緒にいなかった、ということがわかってきたわけです。
次に表3を見てください。クラウス、ケネルという有名な人が、そこに出ているように、お母さんの特徴、収入、社会階層、赤ちゃんの目方、男・女、すべて類似の対照群と長期接触群の2つのグループを作り実験しました。長期接触群というのは、生まれてから退院するまでお母さんのそばに赤ちゃんを置いて、母乳とか抱くとかのふれあいを十分与える群です。対照群は、哺乳のときだけ赤ちゃんを連れてきて、後は新生児室で赤ちゃんを育てたわけです。
表4を見ますと、退院1か月健診のときに、赤ちゃんが診察しているのをお母さんは椅子に座って眺めていたか、「座ったまま無関心」が0点で、「いつも立ったままでながめていた」が3点。それから、子どもが泣いたとき、あやそうと努力したか、「子どもを無視した」が0点で、「いつもあやした」が3点です。そうすると、生後1カ月の時点で、黒いほうが長期接触群です。斜線が対照群ですけれども、長期接触群が明らかに好ましい行動をお母さんがとっていることがわかります。
表5を見てください。これは同じようなことで、そのときの「愛撫行動」と「顔と顔を向かい合わす姿勢」です。これでも長期接触群のほうが対照群よりはるかに好ましい行動が多いということがわかりました。
1年後のことですけれども、表6を見てください。1年後の診察に来たときに、医師の診察中に見られたお母さんの行動を15秒ごとに観察して、お母さんが診察中の医師を助ける行動の回数を示したものです。
これでも明らかに長期接触群の方が好ましい行動が多い。さらに表7のほうは、お母さんの行動で、子どもが泣くときに応えてあやす行動を示したパーセントです。1年たっても、明らかにお母さんは子どもを育てるのに好ましい行動をしていることがわかったわけです。
|
||||||||||||||||||
|
母子健康協会 > ふたば > No.71/2007 > 子どもが育つ保育 > 1.ふれあいの意味 > 新生児期における「ふれあい」の重要性
|
||||||||||||||||||
|