 |
 |
| 第25回 母子健康協会シンポジウム |
 |
保育と食育 |
1.子供の味覚の発達
神奈川県立保健福祉大学教授 前川 喜平 |
|



| 味覚の形成 |
 |

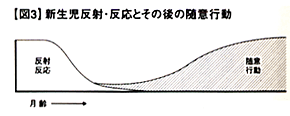 図3を見てください最初のほうは原始反射みたいに、あるところまで来るとだんだん鈍くなって、それと一緒に、いわゆる本来の味覚が育つということになっているのだと思います。 図3を見てください最初のほうは原始反射みたいに、あるところまで来るとだんだん鈍くなって、それと一緒に、いわゆる本来の味覚が育つということになっているのだと思います。
味覚の発達、「preference」といいますけれども、どういうふうに育つかというと、いろいろな実験とか何かを考えますと今のところは、「白い布に絵を描くみたいだ」といいます。だんだんと色を塗るといろんな色が塗れますね。最初から濃い味を使うと、色を塗ると、塗れませんよね。
動物実験で、ネズミに塩辛い餌をやって育てると、あとでも塩辛い餌が好きだとか、栄養のない餌を食べさせておくと、あとでまた食べるとか、そういうことが事実としていろいろわかってきています。
それから、フェニールケトン尿症という特別な代謝異常のお子さんがいます。そのお子さんに、フェニールアラニンが入っていない「ロフェミルク」という特殊ミルクを、乳業会社がつくって飲ませています。そうすると、病気が重症にならないのです。ところが、その味がいかにもまずいのです。それで、周りの人が心配して、味のいいロフェミルクをつくったわけです。さあ喜ぶと思って飲んだら、前のまずいロフェミルクを飲んでいた赤ちゃんが、おいしい味のロフェミルクを飲まない、前のが好きなんです。大和田先生の恩師の北川教授が、そのことを私に話されました。今の話で、少なくとも乳児期からのそういう味覚がある程度メモリーして残って、それが味覚の好みを決めるのだということを話しましたら、1つのそれが裏づけになるような気がしたのです。



|
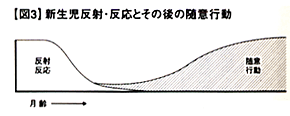 図3を見てください最初のほうは原始反射みたいに、あるところまで来るとだんだん鈍くなって、それと一緒に、いわゆる本来の味覚が育つということになっているのだと思います。
図3を見てください最初のほうは原始反射みたいに、あるところまで来るとだんだん鈍くなって、それと一緒に、いわゆる本来の味覚が育つということになっているのだと思います。