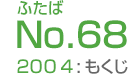| 母子健康協会 > ふたば > No.68/2004 | ||||||||||
|
|
| ■ | 「こどもの心身を蝕む社会環境 NO.2」 - 身辺な環境や幼児教育の大切さ - |
こども心身医療研究所所長 冨田和巳
■はじめに ■社会で求められるもの ■心(知情意)の育ち方■心の危機(心がむしばまれる時代)■素因と子どもの身近な環境
■おわりに
| ■ | 「幼稚園・保育園に通う年齢のこどもの腎臓病」 |
東京大学大学院医学系研究科小児医学講座教授 五十嵐 隆
■1:急性腎炎 ■2:ネフローゼ症候群 ■3:尿路感染症 ■4:無症性血尿| ■ | 「子どもの病気にステロイドを使うといわれたとき」 |
山口大学医学部生殖・発達・感染医科学講座小児科学教授 古川 漸
■1:ステロイド薬とは ■2:ステロイド薬の副作用はなぜおこるのか■3:ステロイド薬はどのように使うべきか
■4:ステロイド薬による成長障害
■5:どのような病気にステロイド薬をもちいるか
■6:ステロイド薬の投与法
| ■ | 「子どもの健康とお砂糖」 |
| ■ | 第24回 母子健康協会シンポジウム 「保育におけることばの問題と対応」 |
1:言葉の発達とその規定要因
白百合女子大学教授 秦野 悦子
■話し言葉の獲得■言葉の発達を支える生物学的基礎/言葉の発達を支える認知的基礎
■対人関係成立が言葉のやりとり基礎
■やりとりを支える社会的基礎 ■音韻体系発達と音声の発達
■語彙・語意の獲得から構文・文法規則の獲得
■身近なできごとに対してスクリプトを形成する
■言葉の発達をとらえていくときの視点
2:ことばの遅れと対応
神奈川県立保健福祉大学教授 前川 喜平
■ことばの発達の必要条件 ■ことばの獲得 ■言葉の遅れの鑑別 ■遅れの対応3:吃音など構音上の問題とその対応
国際基督教大学教授 栗山 容子
■ことばをモニターする ■構音の発達とその問題■吃音傾向にあった子ども ■子どもとの関わり
■吃音は遺伝するか?/専門的な指導を受け入れる心の準備
■いつ指導を始めるのがよいか/どのような方法で? ■専門機関
4:討議
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
母子健康協会 > ふたば > No.68/2004