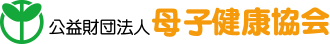小児がん患児との出会い
1981年(昭和56年)に聖路加国際病院で小児科医として臨床研修を開始した当時は、小児がんと診断された患児でも治るようになり始めた頃でした。米国で学び日本に初めて本格的な小児がん治療を導入した西村昻三先生が部長を務める同病院で、米国でのクリニカルフェローの経験を積んで帰国したばかりの細谷亮太先生が、患児と保護者に正確な説明をし、完治を目指した治療に積極的に取り組んでいるときでした。小児病棟には急性リンパ性白血病(ALL)を始め、多くの小児がん患児が入院しておりましたが、病院の特殊性もあって他病院からターミナルケアのために紹介されてきた患児も多く、私たち小児科研修医は初期治療からターミナルケアまでを経験させていただきました。
聖路加国際病院小児科病棟の一画には、当時としては珍しい成分輸血室が設置されており、IBM2997という器械でドナーから血小板や白血球(顆粒球)を採取し、成分輸血として治療に使っていました。日赤に依頼して入手する血小板製剤は200mlの献血由来血小板で、1回の治療として10パック程度輸注するのが普通の時代でした。その頃から成分輸血の効果の高さを実感しておりました。ドナーからの顆粒球輸注も普通に行っていましたので、その後に徳島大学で末梢血幹細胞移植を開発する技術的基盤はこの時代にできたのかもしれません。
聖路加病院で学んだ4年間に、たくさんの子ども達の死亡診断書を記載させていただき、医師として本当に多くのことを学ばせてもらいました。後年、大学教授として担当した学生授業でも、「医師にしかできない仕事はなんだ」と学生に問い、「私は死亡診断書を書くことだと思っている」と伝えていました。いまでも死亡診断書を書いた全ての子ども達のことを覚えていますし、2021年であればもっと違う方法で助けられたのにと思い出します。
一方で、自分の経歴の各時期に自分が一生懸命に取り組んでいたことと患児の発症時期や病態などの組み合わせがよく、いい結果を出せたことが稀ながらありました。その中には、医師や弁護士になって活躍する元患児もおり、彼らが大きな社会貢献をして次の世代へつないでほしいと思います。私たちの世代は、このようにほとんど治らなかった時代から大部分が治る時代にかけて小児科医として経験させてもらった幸運な世代だと思います。