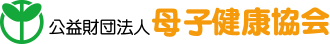造血細胞移植術について
長年、骨髄移植、臍帯血移植、末梢血幹細胞移植に従事し、それを利用した小児がん治療の必要性を究明してきたつもりですが、患児の状態は様々で簡単に説明できるものではありません。よく勘違いされるのですが、「ドナーさえいれば助かる」「移植をすれば治る」という発想は正しくありません。白血病や固形腫瘍の治療において、移植術そのものが根治療法になることはありません。強力な化学療法や放射線療法でがん細胞を根絶するために移植術を利用するというのが基本的な考えです。これらの移植術で治せると断言できるのは、重症再生不良性貧血や骨髄異形成症候群のような、「造血幹細胞病」だけです。白血球、赤血球、血小板の基になる細胞の「造血幹細胞」に病気の原因がある場合に根治療法になりえます。急性白血病や神経芽腫などの固形腫瘍は、造血幹細胞の病気ではありませんので、造血幹細胞移植をしても、移植だけでがん細胞の根絶ができるわけではないのです。そのため、移植が成功したとしても再発の可能性はあります。特に、移植前に抗がん剤感受性がない、つまり抗がん剤が効かなくなった患児では根治の期待は極めて低くなります。
小児がん治療の現場にいる間ずっと、造血細胞移植術は「最後の切り札」ではなく、「最初の切り札である」と言ってきた理由はここにあります。体力的にも元気で、抗がん剤感受性がある時に移植治療を併用しなければ意義は小さいと考えておました。もちろん、全ての患者さんに当てはまるわけではないので、主治医とよく相談して決定することが重要です。なぜ最初の切り札にできなかったのか、それは単純明快で、移植治療そのものが安全性の観点から命をかけた治療だったからです。思い返せば、辛い思い出がたくさん蘇ってきます。そのため、造血細胞術は非常に乱暴な方法で、図2に示すような「金属バットで殴って治療するように感じている」と言っておりましたが、このような表現も最近では不適切で、特に約20年前に、抗がん剤の一つであるフルダラビンの導入によって印象が大きく変わりました。今後も、新しい薬剤の開発でさらにスマートな治療法になると思います。

図2.1990年の造血細胞移植術に対する筆者のイメージです。
体内の残存がん細胞を根絶するための治療は、金属バットで殴るがごとくの印象でした。
(画:徳島大学小児科 中川竜二先生)